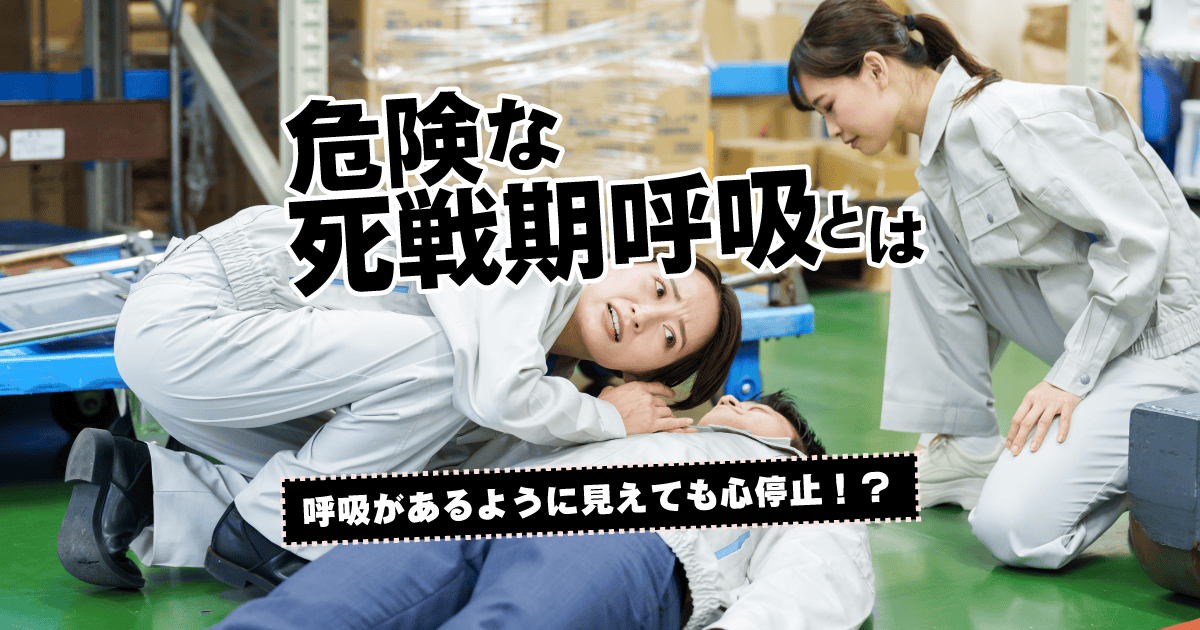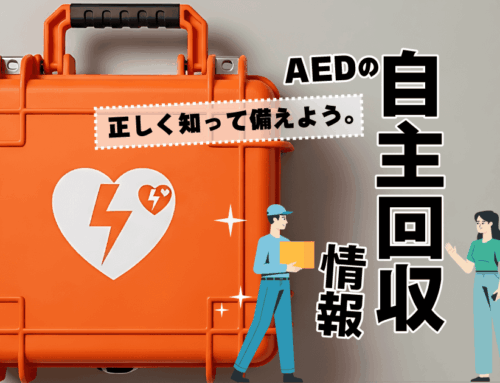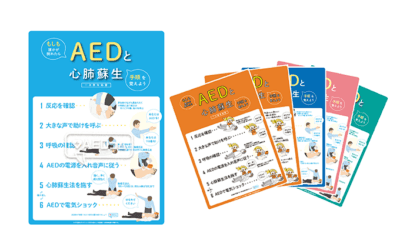【参加レポート】AEDマップはどう変わる?「AEDマップ統合推進シンポジウム」
一般市民によるAED使用が解禁されてから約20年が経過し、使用件数は増加傾向です。しかし、目撃された心原性心停止のうち、実際にAEDによる電気ショックが行われたのはわずか5%に過ぎない現状が問題視されています。
救命率を高めるには「作動するAED」の正確な場所を知れるマップが必要不可欠です。日本には複数のAEDマップがあるものの、どのマップも情報の網羅性または信頼性に課題があります。
2025年8月に「全国AED設置情報データベース/日本AEDマップ」の開発・整備における構想や今後の展望についてのシンポジウムが開催されました。
本記事では、シンポジウムで語られた印象的な講演内容についてまとめました。まとめだけご覧になりたい場合には、最後にまとめておりますので、コチラをご覧いただけたらと思います。
開会の辞
日本AED財団理事長の三田村 秀雄氏(国家公務員共済組合連合会立川病院 名誉院長)は開会の辞で、AEDを使う人のほとんどがAEDについて詳しくない、あるいは知らない人であることを忘れてはいけないと強調しています。
現場で目撃のある心原性心停止は、AEDによる電気ショックを行えば50%の命が助かります。しかし、その恩恵にあずかれたのはわずか5%(※ショックを実施したケースのみで、AEDを使った総数から割り出した数値ではない)に過ぎません。適応外だったケースもあるが、AEDが近くになかったり、あっても見つけられなかったりするケースが多いのではないでしょうかと指摘しました。
三田村氏は、小学生のときにAEDマップを作成した林 陽月さんのエピソードや、大阪府堺市の「まちかどAED」の取り組みを紹介し「マップで救える命がある」と語りました。
使う側の視点に立ち、複数のAEDマップをひとつにまとめる重要性を強調しています。マップの統合は、日本の救命インフラにとって極めて重要な位置づけであるとも述べています。
第一部講演:「AEDマップの過去、現在、未来」
座長は、国士舘大学防災・救急救助総合研究所 所長の島崎 修次氏、東京慈恵会医科大学救急医学講座 主任教授の武田 聡氏が務めました。
最初に座長の島崎氏より「〜公共AEDデータベースの未来構想〜さらなるAEDの使用率を改善するためには」というテーマで講演がありました。
2024年はAEDの使用が一般人に解禁されて20周年であったことに触れ、一般の人々にもっとAEDを使ってもらうことが心停止後の予後を改善するためには不可欠ですと語っています。そのためには「どこにあるか分かってもらう」手立てが重要と強調しました。
講演1:「AEDマップの歴史」
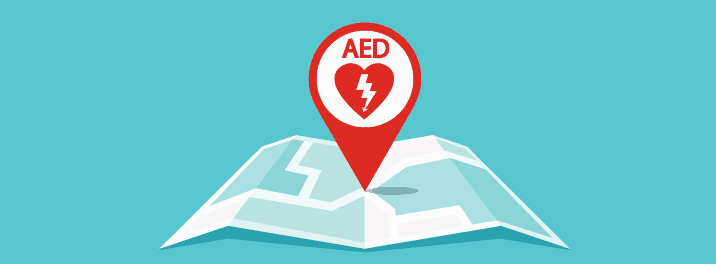
講演:丸川 征四郎氏(医療法人徳洲会集中治療部顧問 吹田徳洲会病院救急・集中治療部 部門長)
丸川氏は、日本のAEDマップの歴史やこれまでの取り組み、台湾の事例などについて紹介しました。
主なAEDマップの一つである「財団全国AEDマップ」では、ピン精度区分表の整備を行っています。AEDの設置年数や、パッド・バッテリーの入力有無によって区分けし評価しています。結果として販売されているAEDのうち、実際に使えるのはわずか20%という現状が明らかになりました。
丸川氏は今後の課題として、以下の2点を挙げています。
- 登録数の伸び悩み:原因としては、AEDを購入しても登録しない人がいるためと分析
- アクセス者の滞在時間が短い:AEDマップが実際に蘇生現場で使われているかは不明
海外の事例として、台湾のAEDマップ「急救先鋒APP」も紹介されました。日本の欠点を克服して作られたマップで、全国規模かつ国の事業として運営されています。
119番と連動し、現場近くの救急ボランティアに通知して、CPRやAED実施の応援を要請する仕組みです。AEDの登録は日本では任意ですが、台湾では法律で義務付けられています。
【参考】
台湾では「急救先鋒APP」を導入し、CPR実施率と生存率の向上が認められました。2015年のバイスタンダーによるCPR実施率は20%に留まっていましたが、2022年には60%に増加しています。CPRが実施されるようになり、生存率も2.3%から4.8%まで改善しました。
講演2:「AEDマップの現状と課題」
講演:田邉 晴山氏(救急救命東京研修所 教授)
田邉氏は、AEDの現状とマップ統合の必要性について講演しました。
日本でのAED販売台数は累計で150万台です。古くなったAEDの更新もあるため、現在の設置台数は約71万4千台となります。これは、歯科医院(約6万6千件)やコンビニエンスストア(約6万件)1店舗のまわりに、約10台のAEDがある計算です。
2023年(令和5年)に一般市民がAEDによる電気ショックを実施した例で1か月後の生存率は54.2%、社会復帰率は44.9%でした。何もしなければ10%以下であることから、AEDはライフラインの一つとなっていると強調しました。
一方で、年間約14万人の心停止のうち心原性心停止は約9万人で、目撃された約28000件のうちAEDによる電気ショックが行われたのは約1400件と、わずか5%にとどまっている現状も指摘しました。この5%という数値は、過去10年間ほぼ変わっていません。
AEDの使い方が分からない、あるいは必要かどうか分からないという問題は、119番での助言やAED本体の音声ガイダンスによって改善されてきました。しかし、AEDが近くにない・どこにあるのか分からないという問題は、119番では解決できません。
「どこにあるのか分からない」という課題をマップの整備で解決しようとしています。しかし、現状どのマップも、すべてのAED設置場所をカバーしていません。
複数のマップが存在する問題点としては、以下の点が挙げられます。
- 消防や一般市民:どのマップを頼ればいいか分からず、必要な情報を迅速に得られない
- 設置する側:登録や情報更新の負担が大きく、正確性の低下をまねくリスク
- AEDマップ事業者:システム投資のコストやリソースの非効率な利用
これらの問題点から、全国AED設置情報データベースの整備という形で、マップの統合が必要であると結論付けました。
講演3:「AEDマップを活かした救命の未来像」

講演:石見 拓氏(京都大学大学院医学研究科社会健康医学系専攻予防医療学分野 教授)
石見氏は、日本やデンマークの事例をもとに、デジタルの活用など救命の未来像について語りました。
「全国AED設置情報データベース/日本AEDマップ」は、今後5年間での機能活用を目指していると説明がありました。2年目以降には「AED GO」や「LIVE 119」との連携も視野に入れています。その他、以下も進めるように計画中です。
- データの管理
- 消防・自治体への広報
- 新規購入者や市民への周知
2025年の大阪万博では、スマートフォンを活用して心停止現場にAEDを届ける「AED GO」(AED救命システム)を導入中です。
- AED GOとは?
-
アプリを使って救急車の到着前に素早くAEDを運搬して、救命率の向上を目指したシステムです。近くのAEDの場所がアプリ上で分かり、さらに、救命ボランティアにAED運搬の要請ができる仕組みになっています。
【アプリ】消防の119番通報と連携したAEDアプリ「AED GO」のまとめの記事でも詳しく説明していますので、あわせてお読みいただけたらと思います。
「AED GO」を活用した、地域単位での設置情報の実証実験も行われています。「AED GO」では多くの心停止をカバーできるが、活用にはすべてのAED設置場所が正確に分かる必要があるとも指摘しています。
AED救命システムの事例として、デンマークの例が紹介されました。デンマークではAED救命システムにスマートフォンを活用した結果、心肺蘇生やAEDによる電気ショックの実施率が向上しました。実施率向上は、通知で駆けつけた人が心肺蘇生を行っているためと分析しました。
諸外国で実施率が伸びているのにもかかわらず、日本では伸びない理由について「当たり前なのにできていないこと」があるためと指摘しています。
心停止の多くが発生する自宅でのテクノロジーの活用についても紹介されています。デンマークでは、自宅で発生した心停止など目撃者がいない場合でも、デバイスが感知し対応が取られます。ボランティアが駆けつける、家族に知らせる、近くのAEDが光って通知するなど具体的な対応が紹介されました。
第二部パネルディスカッション「公共AEDデータベース構築に向けて」

第二部では、「公共AEDデータベース構築に向けて」と題し、国士舘大学大学院救急システム研究科 研究科長・国士舘大学スポーツ医科学科 教授の田中 秀治氏が司会を務め、以下のパネリストが登壇しました。
- 丸川 征四郎氏(医療法人徳洲会吹田徳洲会病院 救急・集中治療部 部門長)
- 石見 拓氏(京都大学大学院 医学研究科 予防医療学分野 教授)
- 田邉 晴山氏(救急救命東京研修所 教授)
- 片岡 竜彦氏(堺市消防局 救急部 救急課長)
- 山田 卓氏(一般社団法人電子情報技術産業協会(JEITA)/日本光電工業株式会社)
司会の田中氏より「AEDマップの問題点や、統合するのに大切なこと」というテーマの提示があり、活発なディスカッションが行われました。
マップの統合には、コンセプトや思いを一つにまとめることが重要であるという意見がありました。組織それぞれの強みを活かし、共通のテーブルで議論できること自体が大切であると強調していました。
AEDマップの問題点としては、以下のような意見が挙がりました。
1. マップの精度の維持について
精度の維持についての意見がまず挙がりました。AEDマップは情報量よりも正確性が重要だという意見が、複数のパネリストより強調されています。
「取りに行ったけれど、使えない」という事態は、バイスタンダーを一人失うことにつながるためです。「マップを見て取りに行ったのに使えなかったから、命が助からなかったんじゃないか!」と言われるリスクもあります。
2. 住民の認知度について
住民の認知度も課題として挙げられています。AEDを設置している事業者にAEDを現場に持っていくよう電話で依頼した際に、従業員が設置場所を知らないケースがあったと語られました。
3. 情報のタイムラグについて
マップ情報のタイムラグをなくすには、人の手で登録するシステムには限界があるという意見もあります。正確性を維持するには、人手、お金、知恵が必要です。現実的な問題としても統合が必要であるという意見もありました。
4. 設置者や行政、販売店などとの協力体制
設置者や行政、販売店などの協力が必要という意見も語られました。AEDについて外国では国として取り組んでいますが、日本では任意性が高くなっています。全国民のベクトルを合わせるには、公共機関の協力を得たいという意見もありました。
マップの作成には、一般市民の声を反映させるのが重要という意見もあります。「全国AED設置情報データベース/日本AEDマップ」は、一般市民の目線をもとに開発・改善していく方向であるとの説明がありました。
閉会の辞
閉会の辞で横田 裕行氏(一般財団法人 日本救急医療財団 理事長)は、今回のシンポジウムのキーワードが「5%」であったと強調しました。
目撃のある心原性心停止で、バイスタンダーが胸骨圧迫を行ったケースは約60%です。6割が胸骨圧迫をしているのにAEDによる電気ショックは5%しかないことが、今回のシンポジウムでの問題であると指摘しました。
現状のAEDマップは「認知度」と「精度」が課題であると語りました。精度の高いAEDマップがあれば、北欧に負けない蘇生率と生存率を目指せるのではないかという意見で締めくくりました。
おわりに~AEDマップの統合で「いつでも、誰でもAEDを届けられる」未来へ
今回のシンポジウムのまとめは以下のとおりです。
シンポジウム内容のまとめ
- 目撃された心原性心停止のうち、一般市民によるAEDによる電気ショックが行われたのは約5%に留まっています。5%という数値は過去10年間ほぼ変わっていません。
- AEDによる電気ショックの実施率が低い原因に「AEDがどこにあるのかわからない」という問題があります。現状を改善するために、AEDの設置情報を網羅的かつ正確に提供するマップの開発・整備を開始しています。
- 日本には複数のAEDマップが存在するものの、情報の網羅性や信頼性が課題です。複数のAEDマップが存在することで利用者の混乱や情報更新の負担増を招き、正確性が低下する原因となっています。
- 台湾やデンマークなど諸外国は、心肺蘇生やAEDによる電気ショックの実施率の向上に国として取り組み一定の成果が出ています。
- 日本で心肺蘇生やAEDによる電気ショックの実施率を上げるには、全国民のベクトルを合わせるのが重要です。
シンポジウムでは、AEDマップが複数あることの問題点を指摘しています。現状ではどのAEDマップを使うか選ぶ手間がかかり、タイムロスが発生しやすくなります。
また、バイスタンダーが「ほかのマップを使えば、より早くAEDを見つけられたかもしれない」という自責の念にかられる懸念もあります。AEDマップが1つになれば一般市民の負担が軽減され、使用率の向上が期待できると感じました。
日本ではAEDマップの登録や「AEDを貸し出す・貸し出さない」は設置側の任意になります。AEDマップの登録率を向上させるには、設置者の負担を軽減する対策も必須です。マップの統合で手間が軽減されれば、正確な情報提供が期待できます。
今回のAEDマップの統合により、正確なAED設置情報を必要なときに誰でも活用できる社会になればいいと期待しています。
シンポジウム情報
| 主催 | 公益財団法人 日本AED財団 |
|---|---|
| 協力 | AED設置情報統合整備活用検討委員会 |
| 日付 | 2025年8月23日(土) |
| 会場 | セコムホール(セコム本社ビル2階) |
| 住所 | 東京都渋谷区神宮前1-5-1 |
注記
本記事に記載されている数値・内容は、登壇者の講演やコメントを筆者が当日現地で聴講し、聞き取った情報をもとに構成しています。そのため、発言の解釈や聞き取りに誤りが含まれる可能性があります。内容の正確性には十分配慮しておりますが、後日登壇者や関係機関から公式なデータや発言の確認が取れた場合には、適宜修正・更新を行います。